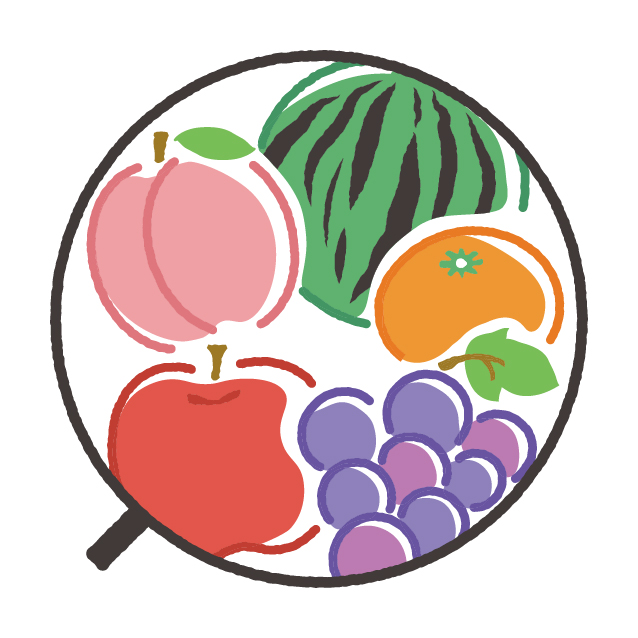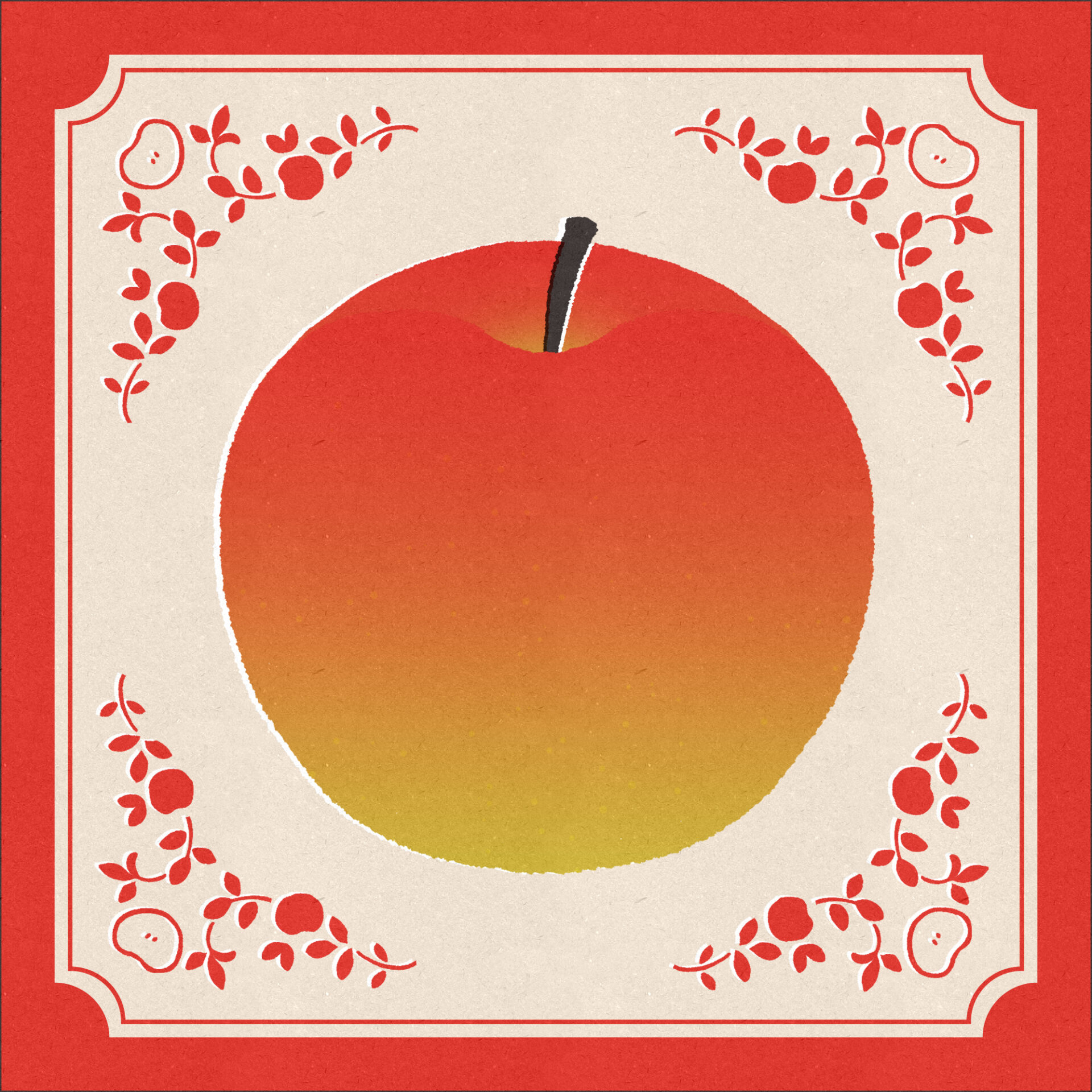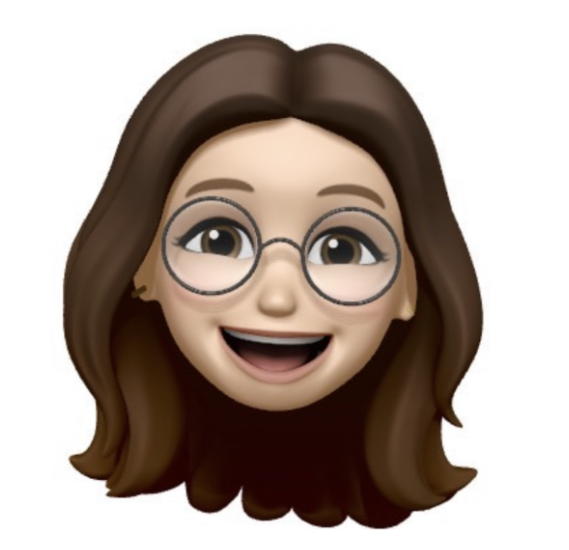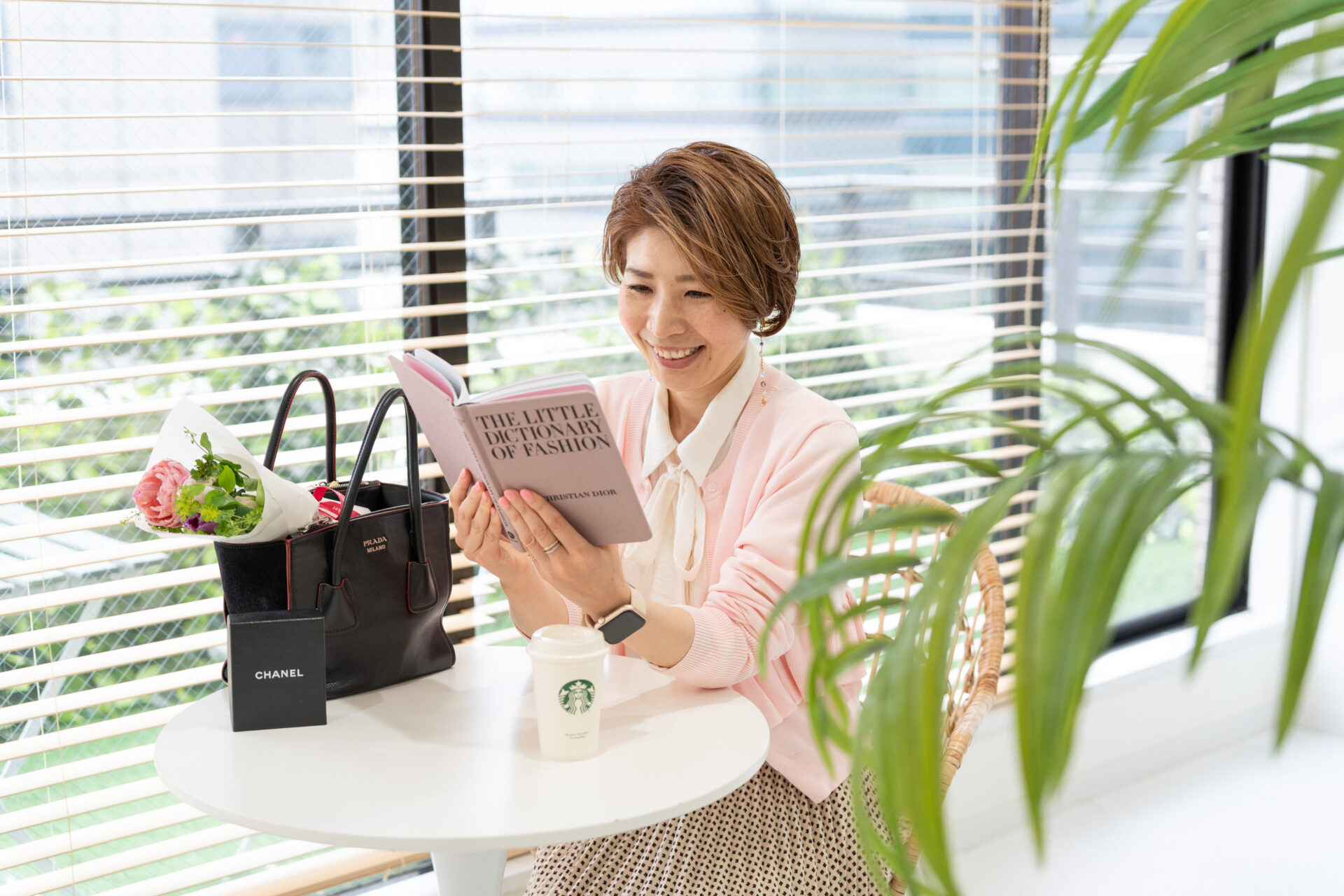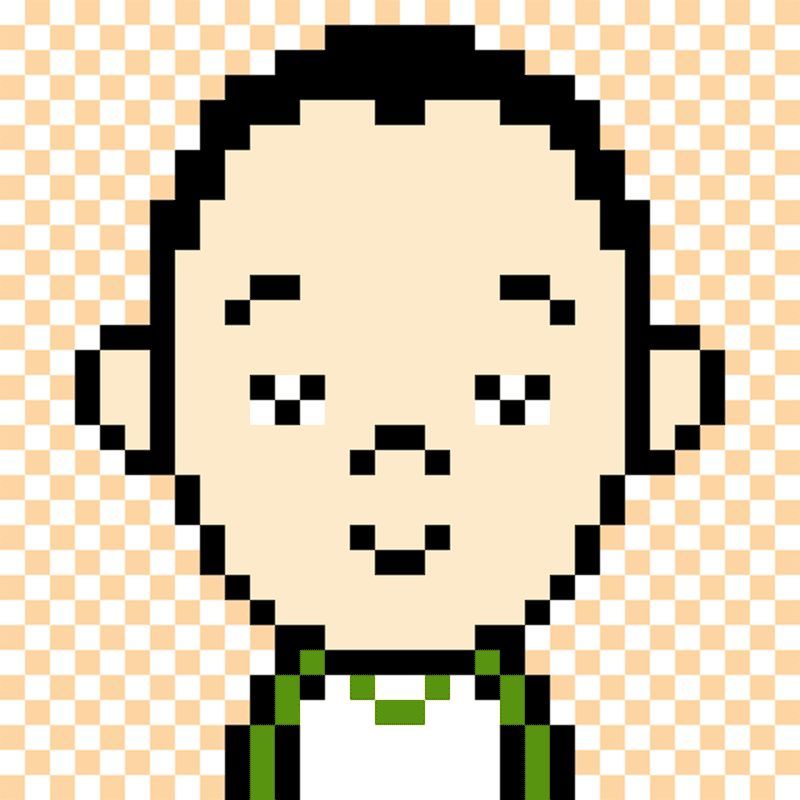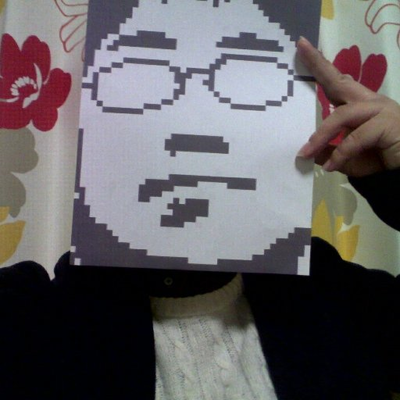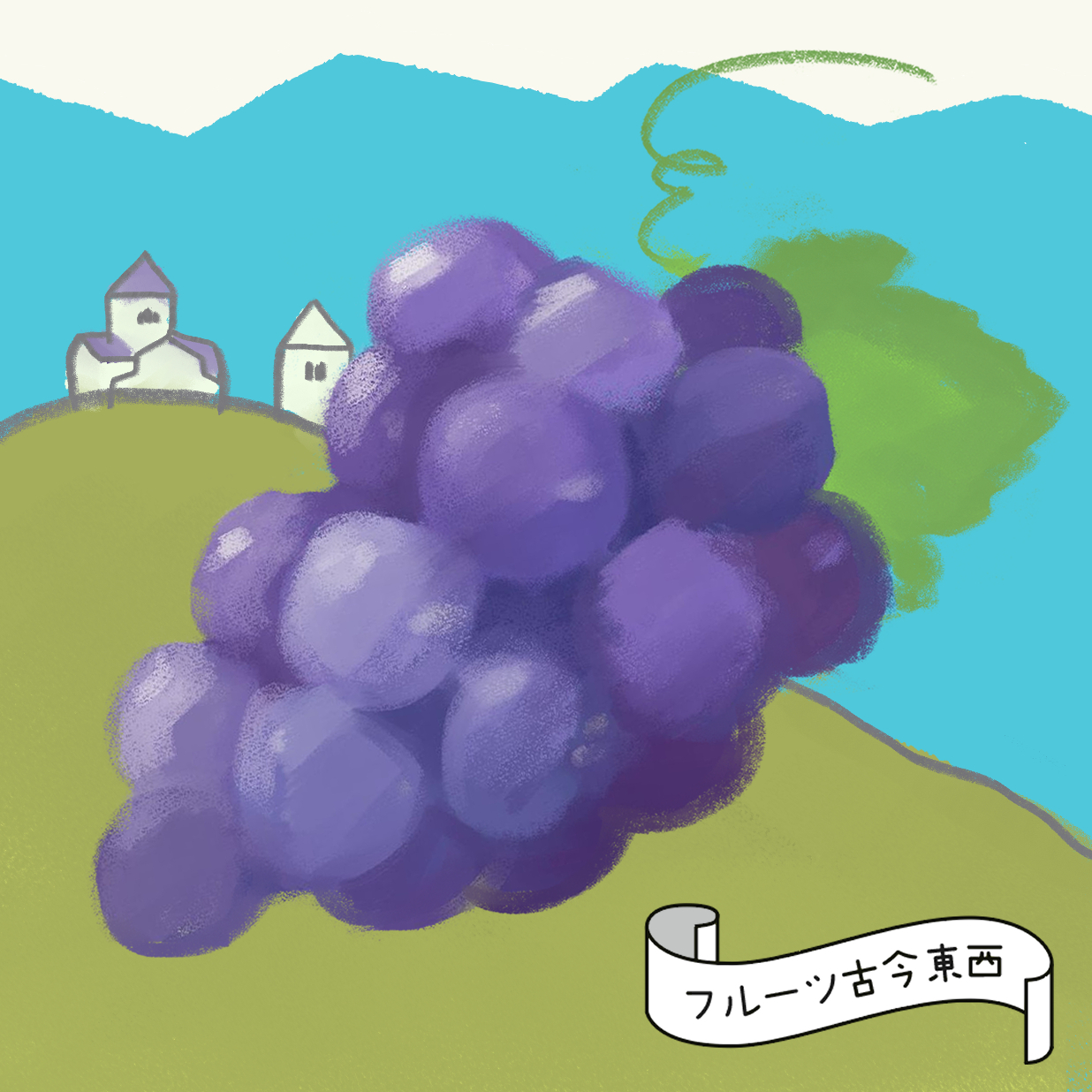
今回は、秋が旬のフルーツである「ぶどう」の歴史について。皆さんはぶどうがお好きですか?
巨峰やデラウェア、ピオーネなどに加えて、近年ではシャインマスカットのように皮ごと食べられて種がないぶどうも多く登場し、年々人気が高まっています。しかし、僕がこの業界に入った頃は、ぶどうは今ほど人気のあるフルーツではありませんでしたので、シャインマスカットは本当に革命的な存在だと感じています。
さて、そんな大人気のぶどうはどこで生まれ、どのように人々と関わり、いつ日本にやってきたのでしょうか?
ぶどうの起源と世界への広がり
ぶどうというと、巨峰やデラウェア、シャインマスカットなど、そのまま食べて甘くて美味しいフルーツを思い浮かべますよね!
僕たち日本人にとって、ぶどうといえば生食が一般的ですが、実は世界的に見ると、生で食べることは珍しく、ほとんどがワインの原料として使われているのです。
ぶどうの原産地は中近東とされており、太古の昔から野生のぶどうが栽培されていました。紀元前6000年頃には、現在のジョージア地方で栽培されていたと考えられるほど、歴史のあるフルーツなんです。そこから西方へ伝わって、ヨーロッパに広まっていったと考えられています。
ぶどうは西洋を代表するフルーツであり、西洋人にとって生命の源ともいえる重要な存在でした。有名な品種として「マスカット・オブ・アレキサンドリア」があります。この品種は日本を含め、現在でも世界中で栽培されていますが、その先祖についてはまだ解明されておらず、原種に近い品種とされています。
古代ギリシャやローマでは、ぶどうは神々への捧げ物としても重宝されていました。ギリシャ神話では、豊穣の神ディオニュソス(バッカス)がエーゲ海の人々にぶどうの栽培法やワインの醸造技術を伝えたとされています。
その後、ぶどうの栽培は地中海地域を中心に広まり、各地で独自の品種が育まれました。特にフランス、イタリア、スペインは、今日でもワイン生産の中心地として知られています。
さらに、ぶどうはシルクロードを経由して中国に広まり、大航海時代には南米諸国などの植民地にも西洋人によって栽培技術やワイン造りが伝えられました。
他にも、古代エジプトやメソポタミア文明の遺跡からも、ぶどうの種やワイン製造に関する証拠が見つかっており、ぶどうが古代から人々に愛されていたことがわかりますね。

ヨーロッパブドウとアメリカブドウの違い
ぶどうは大きく分けて、「ヨーロッパブドウ」と「アメリカブドウ」に分けられます。
あまり聞き慣れないかもしれませんが、日本でよく見かけるのはアメリカブドウと呼ばれる品種です。
ヨーロッパブドウは、先ほどお話しした通り、中近東からヨーロッパに広まった品種のことです。一方で、アメリカブドウとは、古くからアメリカに自生していた野生種のぶどうの品種群を指します。
その違いは、ヨーロッパ系のぶどうはマスカットのように華やかな香りが特徴で、皮ごと食べられる甘いぶどうが多いです。一方で、アメリカブドウは寒さや病気に強く、皮が残りやすいけれど、独特の強い香りがあるのが特徴です。この香りは「フォクシー香(狐香)」と呼ばれますが、実際に狐の香りがするわけではありません。これは、かつて西洋のワイン専門家がこの香りを「野蛮だ」と差別的に表現したものが、そのまま現代に残ってしまったのです。日本でも馴染みのある、個性的で素敵な香りです。
ヨーロッパブドウは主にワイン作りに利用されてきましたが、アメリカブドウはワインに適していないため、現地では主にジュースとして親しまれてきました。アメリカブドウの栽培の歴史は植民地時代以降、約200年と比較的浅いですが、日本との関わりも深いので、次にその点についてお話ししようと思います。

日本のぶどう栽培の歴史と進化
日本でのぶどう栽培の歴史は、中国から伝わり、奈良時代(710~794年)まで遡るとされています。その後、現在の山梨県甲斐国の勝沼地方で栽培が進み、特に「甲州」と呼ばれるぶどうが山梨県の特産品となりました。
本格的な栽培は明治時代に入ってから始まりました。欧米からは新品種がどんどん輸入され、世界に対抗するために、ワイン造りを目的として国を挙げてヨーロッパブドウの栽培が試みられ、国営のブドウ園も作られました。しかし、この農園はわずか6年で閉園に追い込まれてしまいました。
それはどうしてでしょう?
実は、ヨーロッパブドウの多くは乾燥地帯を好む品種で、病気にも弱かったので、日本の気候に全く適さず、栽培ができなかったのです。一方、アメリカブドウは日本の気候に適していて、病気にも強いため、次第に定着しました。しかし、前述のように、アメリカブドウはワイン造りには向いていなかったため、日本では「生食用果実」としての栽培が主流となり、現在でもぶどうは生食用のフルーツとして親しまれている訳です。
昭和時代にかけて代表的な品種として登場したのは、アメリカ系の「デラウェア」や「キャンベル・アーリー」でした。しかし、日本人の気質なのか、どうしても「マスカットも栽培したい」という思いが強く、アメリカブドウとの交配が繰り返されました。こうして「巨峰」や「ピオーネ」といった品種が誕生して、現在では多くの品種が生まれています。これらのほとんどが、ヨーロッパブドウとアメリカブドウの交配種となっています。

ぶどうの名前の由来
ぶどうの学名は「Vitis vinifera」で、ラテン語で「ワイン用の果実」という意味でした。
日本での「ぶどう」という呼び名は、紀元前の中央アジア、現在のアフガニスタンでの呼び方「ブーダウ」に由来しています。それが中国に伝わる際に使用された「蒲陶」が次第に変化し、「葡萄」という漢字が日本に伝わってきました。
「葡萄」という漢字は、房を抱える姿と容器に入れてワインを作る姿を表しているとされています。
余談ですが、日本に自生していた野生種のヤマブドウの中に「エビヅル(古名はエビカズラ)」と呼ばれていたぶどうがあり、今でも日本では「エビ」がぶどうの古名として知られています。「葡萄」と書いてエビとも読むんですよ。
なんで「エビ」?となりますよね。ぶどうの実が昔の人々には海老の目のように見えたそうです。
さらに、日本でお馴染みの唐草模様、よく泥棒が描かれている頭巾の模様も、ぶどうの葉に由来しているんですよ。

ぶどうの普及と日本のワイン文化
ぶどうの歴史を知ると、中東からヨーロッパにかけての歴史と深く関わっていることがわかります。大航海時代に世界に飛び出した西洋人がワインに焦がれて、世界各国でぶどうの栽培を広めていった結果、現在ではぶどうが広く普及しています。
現在、日本のぶどうのクオリティは高いと評判で、シャインマスカットを中心に世界に輸出され、大人気となっています。日本はアメリカやメキシコ、南米からもぶどうを輸入しており、在来種として認定された甲州ぶどうを中心に日本ワイン作りも行われ、世界の評価も年々向上しています。
知っておいて欲しいのは、世界のほとんどの国ではぶどうを生で食べることは少なく、主にワインやジュースに加工されるということです。日本に住んでいると考えにくいですが、日本は水資源が豊富だったので、フルーツから水分を摂る文化は根付かなかったのかもしれません。

おわりに
ここまでいろいろと難しいお話をしてしまいましたが、覚える必要は全くありません。こんなことを言うと「じゃあ、なんで書いたんだ!」と思われるかもしれませんが、大切なのは美味しく楽しく果物を食べることだと僕は考えています。
現在の日本人のフルーツの摂取量は世界平均を大きく下回っています。フルーツは毎日200g摂ることが推奨されていますが、実際には約120gしか食べられていないと言われています。特に若年層や都市部に住む人ほどフルーツをあまり食べない傾向があります。そこで、一人でも多くの人に果物に関心を持ってもらい、その美味しさを知って食べてもらいたいと、僕たち「フル愛」は活動しています。
興味を持つきっかけとして、僕は歴史についてお話ししていますので、ひとりでも「そうなんだ!」「面白いね!」と思っていただけたなら幸いです。ここまでお読みいただき、本当にありがとうございました。
<フル愛について>
僕たち「フル愛」は、食べ比べ会や市場見学など、果物バイヤーによるイベントを中心にフルーツ普及を目的に活動しています。よろしければ、Xで主に活動していますので、フォローをお願いいたします。
https:twitter.com/neko0v0hentai